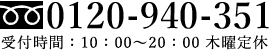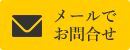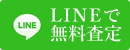金城次郎作品の買取

大切なコレクション、ご自宅で眠っている「金城次郎」作品の売却ならぜひ、やましょうにご相談ください。
金城次郎について
金城次郎(きんじょう・じろう)は琉球陶器の技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された陶芸家です。琉球陶器とは、やちむんともいい、沖縄の言葉で「やち=焼」「むん=物」を意味しています。沖縄の伝統工芸品として現在では全国に多くの愛好家がいます。
琉球陶器の起源は琉球王国の時代まで遡ります。陶器の製法が琉球の人々に伝えられたのは1616年頃で、薩摩から招いた朝鮮人陶工によって製陶技術が伝授されました。当時は荒焼(あらやち)という釉薬を使用しない低温焼成の陶器がつくられており、琉球で本格的に焼き物づくりが開始された時期とされています。
1682年に各地に分散していた窯が統合され、那覇市の壺屋に窯場が誕生。これが後に陶器の一大産地となります。明治時代に入り、文明開化の世と共に衰退の色をみせた琉球陶器ですが、1926年ごろに起こった民藝運動(柳宗悦らによって提唱された考え。実用性の中に美しさを見出す“用の美”。名もなき職人がつくる日用の工芸品に美を見出すこと)によって全国にその魅力が伝えられることとなったのです。
この民藝運動と金城は深い繋がりがあり、日本民藝館には金城の作品が現在も所蔵されています。金城次郎は、1912年12月に沖縄県那覇市に生を受けます。1919年に真和志尋常高等小学校入学した後、1924年に新垣栄徳の製陶所にて陶器製造の見習工として働き始め、翌年には那覇市壺屋の名工として知られる新垣榮徳に師事。同年、生涯交流を持つこととなる陶芸家、民藝運動家の濱田庄司との出会いを果たしました。
金城は戦前より、沖縄の伝統的工芸品を高く評価した柳宗悦の民藝論に感銘を受け、制作に励んだといわれています。1936年には泊村屋比久カメと結婚し、長男・敏男を授かり、その翌年には長女・須美子が誕生します。後に熊本輜重隊藤崎部隊に配属されることとなりますが、1939年に制作された雑誌「工藝」第99号以降、同誌で頻繁に取り上げられるようになり、陶芸家として注目を浴び始めた時期にも当たります。
やがて、1943年に次男・敏昭が誕生し、1945年に沖縄戦は終戦を迎えることとなります。金城はまもなく壺屋にて米軍よりかまぼこ形兵舎を払い下げ、自らの工房を築きました。窯は新垣榮徳の登り窯を共同で使用したといわれています。1951年、戦争によって困窮した壺屋の陶工を救済する目的で、民藝関係者の尽力によって琉球民藝展(日本民藝協会主催)が開催されることとなり、作品を出品します。
また、1954年に新設された沖縄美術展覧会(沖展)の工芸部門にも作品を出品。以降、継続して自らの作品の発表の場として出品を続けました。同年12月には、陶工・新垣栄三郎と共に第1回目となる陶芸二人展を開催しています。(この展示は1958年からは小橋川永昌が参加し、三人展として発展していくこととなります。)1955年、国展に初入選を飾り、以後連続入選を果たす金城。
この頃は、栃木県にある益子や鹿児島県の龍門司などの名窯を訪問しています。機会があれば、丹波や九州などの窯も足繫く訪問したというエピソードも残っており、琉球陶器だけではなく日本の陶器全般に関して研究を重ねていたことが伺えます。翌年には、同展にて新人賞を受賞。1957年には国展で<呉須絵大壺>が国画会を獲得しています。1960年代には全国民藝大会が沖縄で開催され、浜田庄司やバーナード・リーチが壺屋を訪問し、琉球陶器の魅力がより多くの人々に広まるきっかけとなりました。
1969年に国展会友優秀賞、<三彩盒子>ほかが日本民藝館賞を受賞。広島天満屋にて初めての個展を開催するなど陶芸家としてのキャリアを順調に積み上げ、1971年には日本陶芸展に入選を果たします。しかし、この頃は壺屋の登窯から発生する煙が公害問題として問題視されるようになり、沖縄県中部の読谷村字座喜味に自らの登窯を開くこととなりました。この地は後に「やちむんの里」と呼ばれるようになり、現在では全国屈指の名窯場となり、有名な観光地として多くの人々が足を運んでいます。
やがて1972年に沖縄県指定無形文化財技能保持者に認定を受け、翌年には国画会会員となりました。金城は名実ともに日本の工芸界を背負う立場になったといえるでしょう。1977年に現代の名工百人に選出されますが、まもなく高血圧症によって倒れ、4か月の静養を余儀なくされます。手足に麻痺が残るものの復帰し、1981年には勲六等瑞宝章を獲得しています。
精力的に創作活動に励み続けた金城は1985年に沖縄県で初めて重要無形文化財技術保持者(人間国宝)に認定されることとなりました。同年度沖縄県功労章も授与され、1993年には勲四等瑞宝章を受賞した後、2004年に92歳で亡くなりました。2005年には大阪日本民芸館では彼の作品を約170点公開する追悼展示が開催されています。壺屋に生まれ育ち、壺屋焼の伝統を肌で感じながら生涯陶芸制作に心血を注いだ金城次郎。類まれなる技術を駆使して、個性あふれるおおらかな作品を生み出しました。金城は魚をテーマにした作品を多く手掛けていることについて「沖縄は島国で周囲は海だからね。海の生物をテーマにした」「写実ではなく自然だよ」という言葉を残しました。線彫りの技法から生まれる魚文や海老文は、琉球陶器ならではの重さと安定感のある作品に躍動感を与えています。
作品集として「金城次郎の世界」(沖縄タイムス社 読谷村 1985年)、「琉球陶器 金城次郎」(琉球新報社 1987年)、「人間国宝 金城次郎のわざ」(宮城篤正 源弘道監修 朝日新聞社 1988年)、「沖縄の陶工人間国宝金城次郎」(日本放送協会出版 1988年)、著書としては「壺屋十年」(上村正美監修 構成 用美社 1988年)が刊行されています。
代表作品
金城次郎作品の買取事例
金城次郎の参考買取価格
お売りいただけるアイテムがございましたら、お気軽にご連絡ください。
金城次郎作品の査定のポイント
- 01
真贋と共箱の有無
人気陶芸家の金城次郎は沢山の偽物が存在しますのでまずは真贋の確認が必要です。金城次郎は多作だったため箱の無いものも多く、また箱書の文字も統一されておらず本人以外の代筆などもあったと考えられますが朱印に問題がなければ共箱として流通し共箱付きの方が査定はアップ致します。
- 02
傷の有無、状態
カケやニュウなど傷の有無はもちろん汚れなど状態の良し悪しは大きく査定額に影響致しますので査定前に確認してみましょう。
- 03
作品の人気と希少性
同じ金城次郎の作品でも作品、図柄によって査定額が変わります。人気のある魚や海老の模様の掘られた金城次郎らしい作品が人気で高額査定に繋がります。魚紋、海老紋のなかでも大壷や大皿は高値買取が期待出来ます。ぐい呑みなども実用性から割と需要の高い作品です。
関連する展覧会・記念館・美術館情報
お問合せ・ご相談はこちら
「モノ」を大切に、次世代へ
繋ぐ架け橋となります。
全国対応・査定無料
お気軽にご相談ください
買取には本人確認が必要です
古物営業法第15条第1項の定めにより、買取の際にご本人様確認をさせていただきます。
宅配買取の場合は、本人確認書類のコピーを送付してください。
なお、ご提示いただいたお客様の情報は、当店のプライバシーポリシーに則り、厳重に保管いたします。
本人確認書類として有効なもの
- パスポート
- 学生証
- 身体障碍者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード
(Bタイプ)
本人確認書類はいずれもご本人様のお名前・現住所・顔写真・生年月日(または年齢)があり、有効期限内のものに限ります。
※1)2020年2月4日以降に発給されたパスポートは、住所欄が掲載されていませんので本人確認書類としてお取り扱いできません。
買取の流れ
- 01
ご相談・お申し込み
お電話・LINE・メールにてご相談、お申込みいただけます。
査定は無料ですのでお気軽にご利用ください。 - 02
査定・結果のご説明
査定させていただき、買取金額をご提示致します。
相場に基づいた適正査定で安心です。 - 03
お支払い
査定金額にご納得いただけましたらお支払いいたします。
宅配買取の場合は、お振込みとなります。